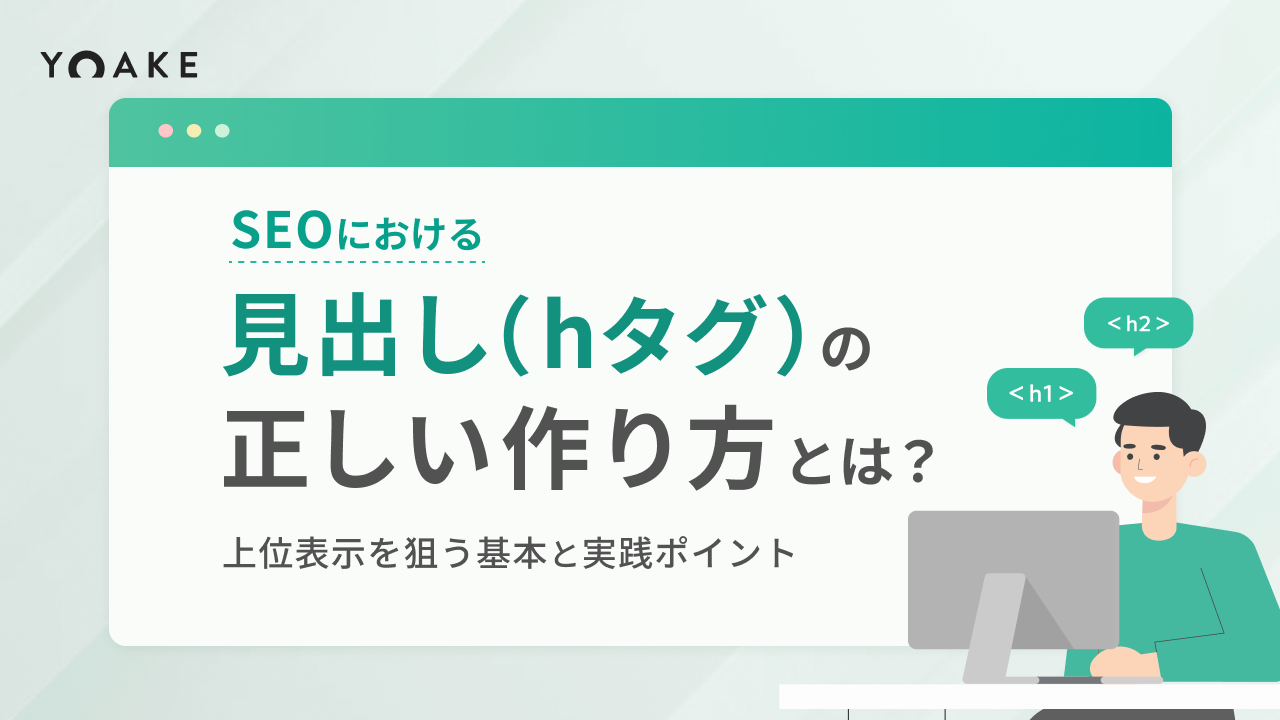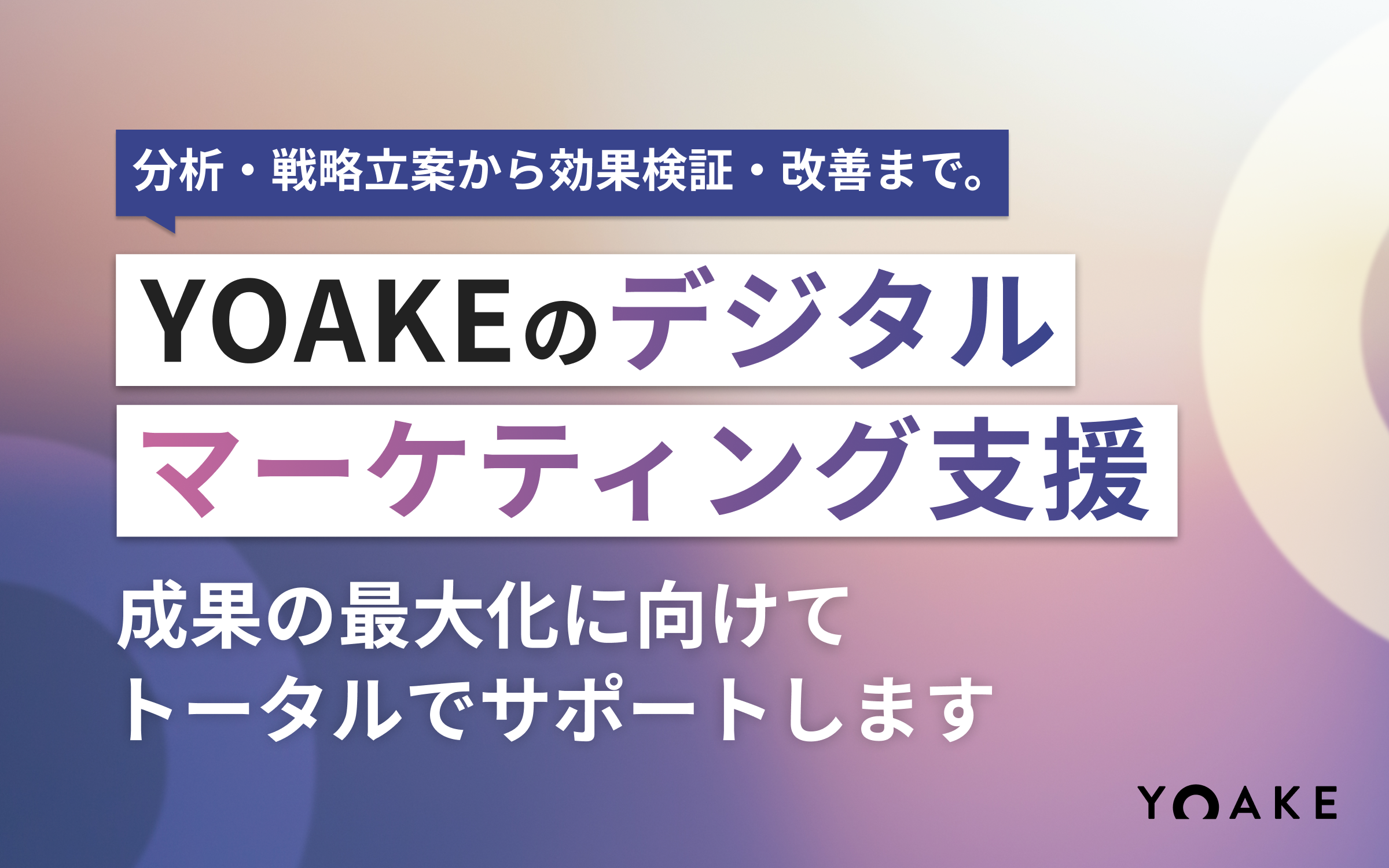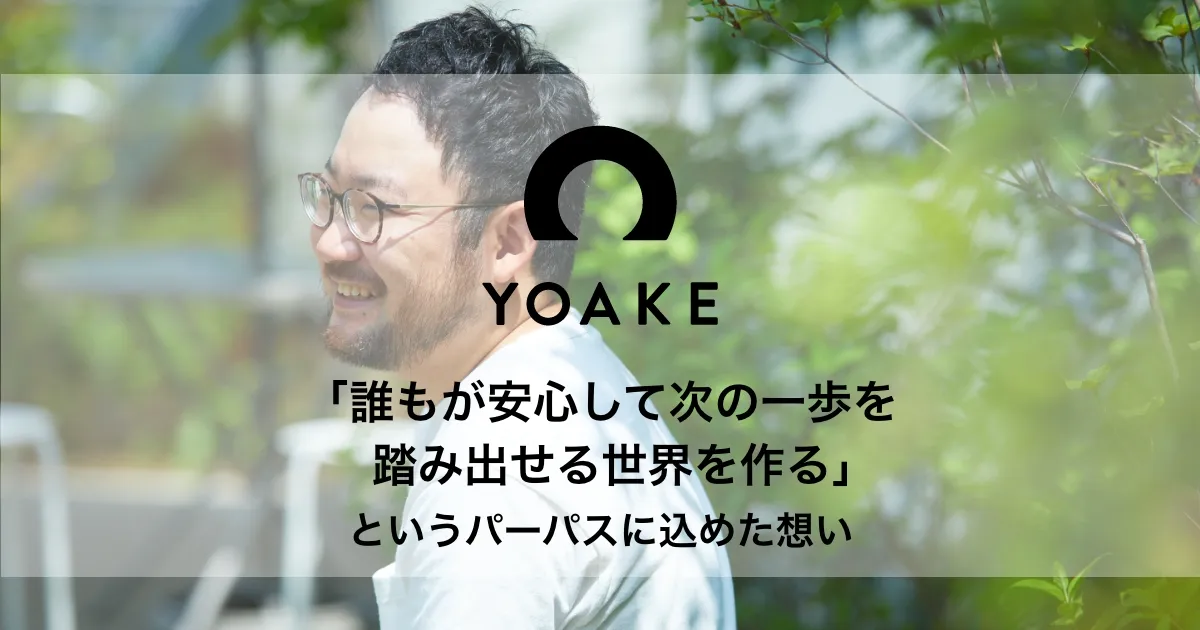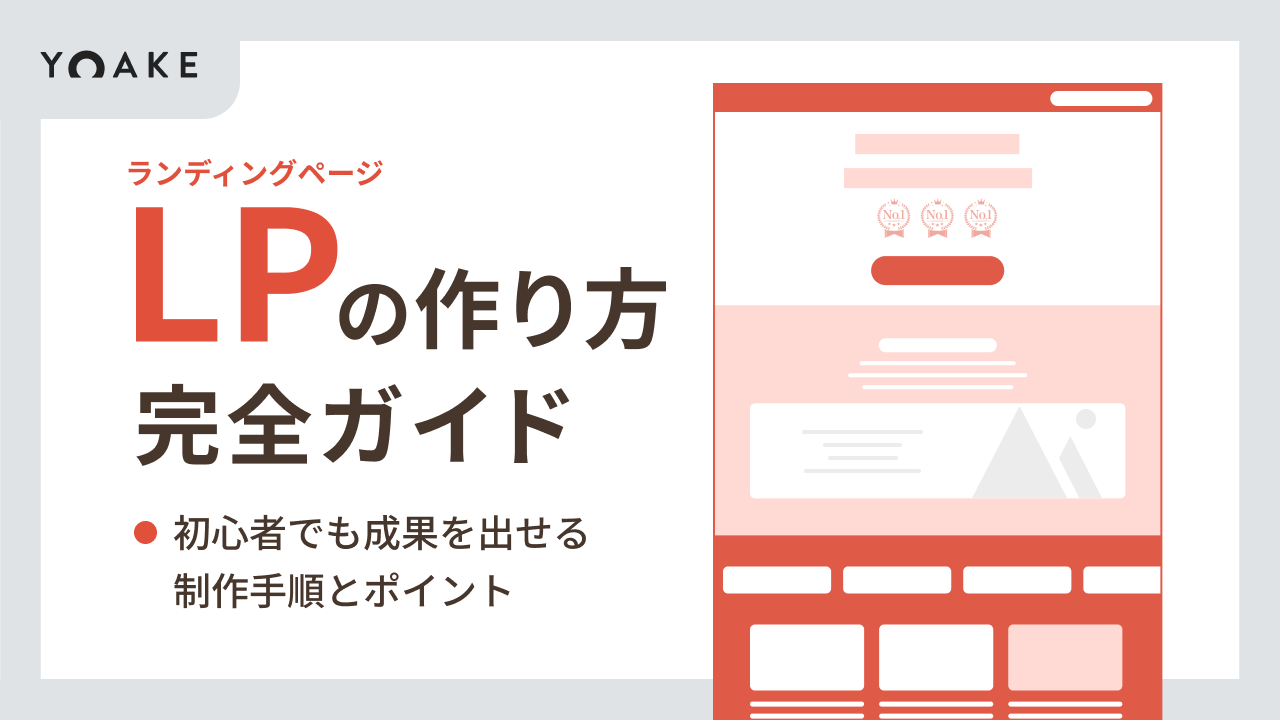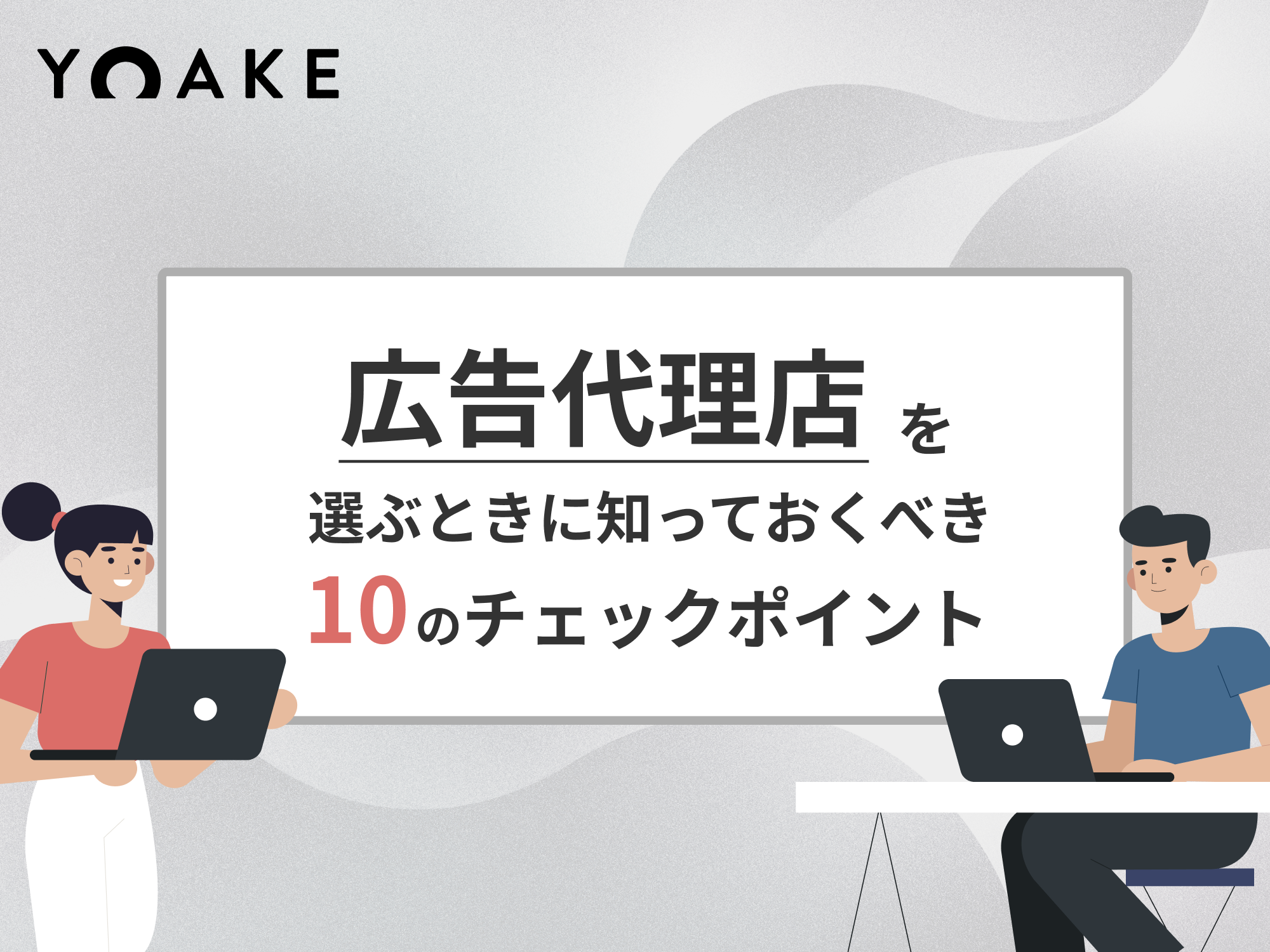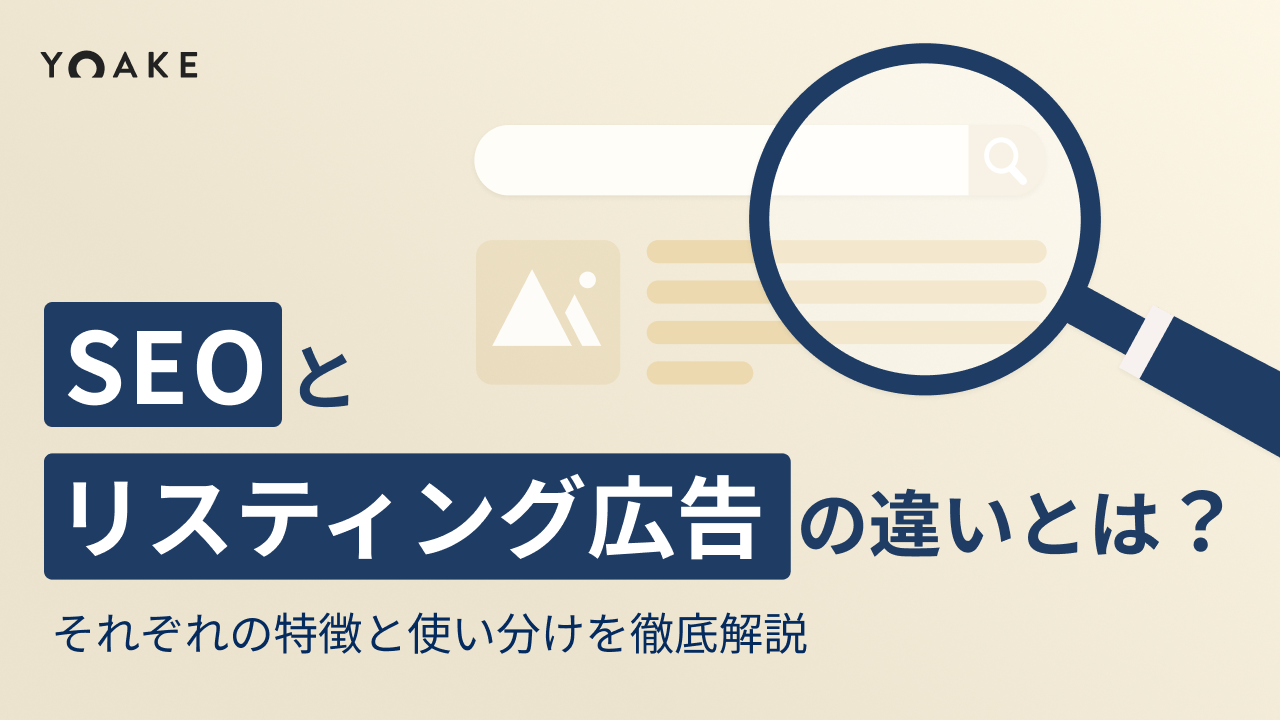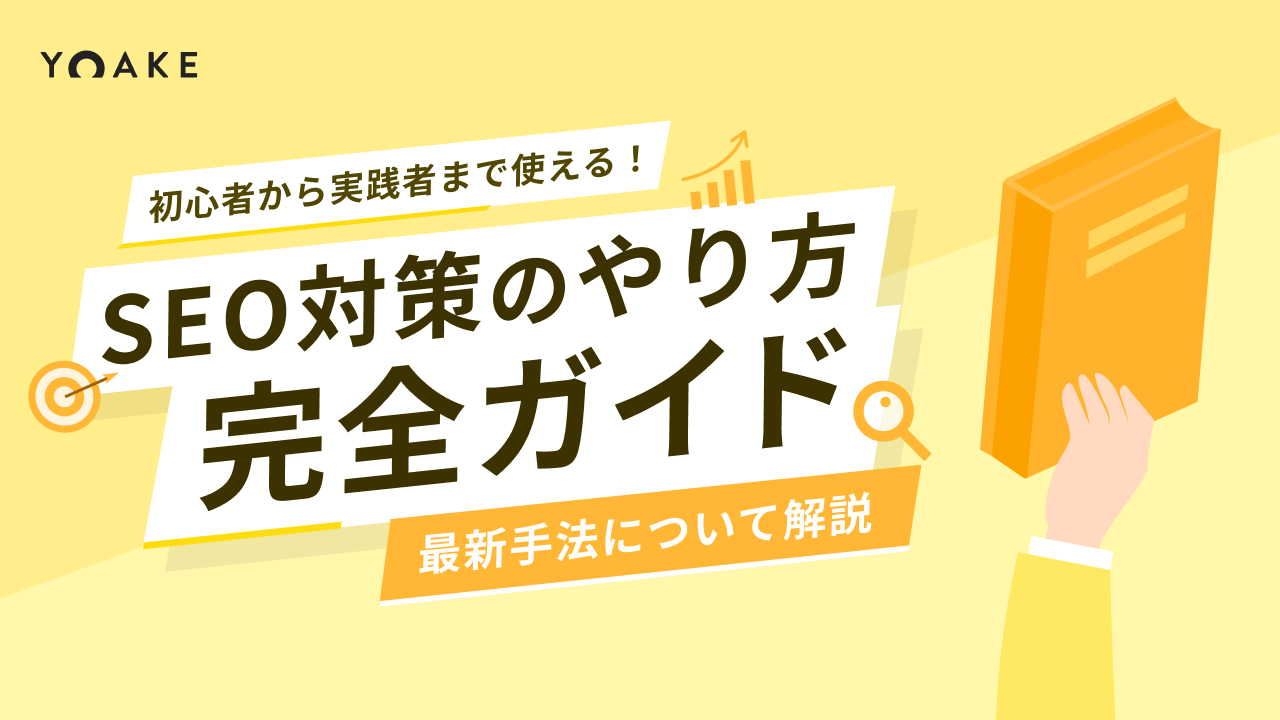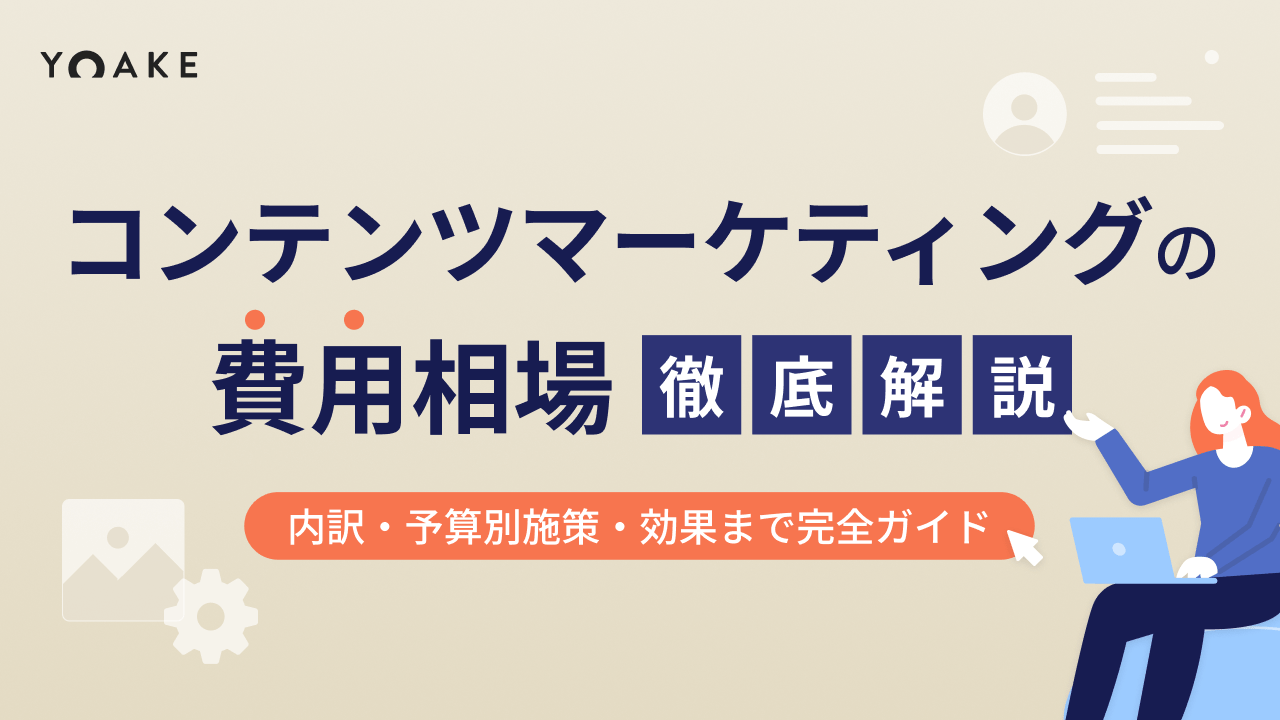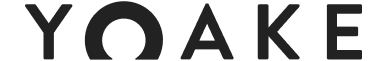SEOにおける見出し(hタグ)とは?
SEOにおける見出し(hタグ)は、h1からh6まで6段階あり、ページの情報構造を階層的に示す役割をもっています。基本的にh1はそのページで最も重要な見出しとして使い、ページタイトルに使用することが多いです。titleタグと同じ文字列にすることも多く、titleタグと同じであっても構いません。h2以下は、h1以下の下位要素を表現します。例えば、記事タイトルがh1、大見出しがh2、中見出しがh3という具合に階層的に使用します。
hタグを使用することで、Googleのクローラーにとっても文書構造を理解しやすくなるため、SEOにおいて非常に重要です。また、見出しに適切なキーワードを含めることで、情報の明確化と検索意図との一致を図ることができ、順位向上につながります。ただし、hタグの使い方を誤ると、クローラーがページ内容を正確に把握できなくなり、順位が上がりにくくなる可能性があります。hタグの適切でない使い方はポジティブ要素にはならずネガティブ要素にしかなり得ないため、細かく管理することが大切です。
SEO観点での見出し(hタグ)のポイント
続いて、検索上位を狙うための見出し(hタグ)設計のコツを紹介します。ここでは、主にSEO的観点での見出し(hタグ)設計について解説します。
階層構造を論理的に整理する
hタグは構造的に正しく使うことで、検索エンジンにもユーザーにも情報が伝わりやすくなります。たとえば、h2の下にいきなりh4が来るように指定するのは避けたほうがよいでしょう。h2 → h3 → h4…と順序立てて設計すれば、ページ全体の論理構造がより明確になります。また、構造が整っていることで、検索エンジンは「このページは情報を体系的に提示している」と認識しやすくなります。ユーザーにとっても、章や節が視覚的に整理されていれば、目的の情報にスムーズにアクセスできるはずです。その結果、離脱率の低下や滞在時間の向上にもつながる可能性があります。特に長文の記事では、目次と見出しがわかりやすく構成されているかどうかが、全体の可読性を左右する重要なポイントとなります。
たとえば、本記事のように以下のような構成にするのが理想です。 '''h1 SEOにおける見出し(hタグ)の正しい作り方とは?上位表示を狙う基本と実践ポイント
h2 SEOにおける見出し(hタグ)とは?
h2 SEOに効果的な見出し(hタグ)を設定するポイント
h3 SEO観点での見出し(hタグ)のポイント
h4 階層構造を論理的に整理する
h4 キーワードを自然に入れる
h4 見出し(hタグ)はシンプルにする(長くしすぎない)
h3 ユーザビリティの観点での見出し(hタグ)のポイント
h4 本文で書かれている内容が一目でわかるような見出し(hタグ)にする
h4 読み進めてもらいやすい表現を意識する
h4 見出し(hタグ)のフォントを揃える
h2 やってはいけない見出し(hタグ)設計の例
h3 キーワードを詰め込みすぎる
h3 本文と関係ない見出し(hタグ)にしてしまう
h3 見出し(hタグ)の階層が乱れている
h3 本文が短くなりすぎる場合は新たに見出し(hタグ)を作らない'''
h1は記事タイトルとして1度のみ使用し、h2は大見出し、h3はそのh2の中に含まれる小見出し、といった構造が望ましいです。h2の内容をh3で分割する必要がない場合は、h2だけにして、無理にh3を使用しないようにしましょう。もちろん、h3をさらにh4を使用して分割したほうが良い場合は、h4を使用して構いません。最大でh6まで使用できますが、あまり細かくなりすぎないよう、h4くらいまでで留めるほうが無難です。
また、これはSEOで必須というわけではありませんが、h3同士やh4同士の粒度は、並列の関係になるような内容にするのが望ましいです。上の例では、「h2 SEOに効果的な見出し(hタグ)を設定するポイント」内のh3がそれぞれ「h3 SEO観点での見出し(hタグ)のポイント」「h3 ユーザビリティの観点でのポイント」と、並列の関係性になっているのがわかると思います。その下のh4も、それぞれ並列の関係になっていますね。このように、hタグの並列性を意識することが、論理的な文章構造につながるテクニックといえます。
キーワードを自然に入れる
SEOの観点では、狙いたいキーワードを見出しに含めることが推奨されます。ただし、単に詰め込むのではなく、ユーザーが自然に読めるような文脈で挿入することが重要です。たとえば「SEO 見出し 作り方」というキーワードであれば、「SEOにおける見出し(hタグ)の作り方を基本から解説」のように、主語と述語が整っている形で表現するとGoogleにとってもユーザーにとっても認識しやすさが担保されます。
とはいえ、過度な挿入や不自然な繰り返しは逆効果となるため、自然な言い回しで必要な箇所に入れることが理想です。具体的には、h2にはキーワードを必須でいれたほうが良いですが、h3やh4まで入れた場合に不自然さが際立つ場合は、なくしてしまっても構いません。また、キーワードを入れる場合は、左寄せ(文頭の方)で入れるほうがSEO的に若干ながら効果が高いとされています。これは、人は左から文章を読んでいくため、キーワードが先に来ていたほうが、自分が求めている情報と関連があると認識しやすいという理由からだと思われます。ただし、左寄せにしたからといってSEO効果が劇的に高まるかというとそうではないので、ある程度意識する程度で大丈夫です。
見出し(hタグ)はシンプルにする(長くしすぎない)
見出しは短く、端的に要点を伝えることが理想です。長すぎる見出しは読みにくくなり、視認性が落ちてしまいます。改行の必要性を感じるほど長い見出し(具体的には40文字以上)は避けたほうが良いでしょう。また、検索エンジンも見出しが簡潔であるほど、主要なキーワードや話題を正確に捉えやすくなります。たとえば「SEOにおいて重要な見出し作成の方法について解説します」といった冗長な表現よりも、「SEO見出しの作り方」や「見出し設計の基本」のように、簡潔かつ要点を含んだ表現が好まれます。文章としての説明は本文で行えばよく、見出しはその内容をひとことで要約する役割と捉えても良いでしょう。シンプルで的確な見出しは、記事全体の構成をすっきりと見せ、ユーザーにも検索エンジンにも優しい設計となります。
ただし、シンプルすぎるあまり他のサイトと全く同じ表現が続くのはSEO的にも避けたほうが良いでしょう。その場合、文字数が増えても良いので、オリジナルの文字列になることを意識することが重要です。
ユーザビリティの観点での見出し(hタグ)のポイント
ここからは、ユーザビリティ観点から、見出し(hタグ)の作成ポイントを解説します。
本文で書かれている内容が一目でわかるような見出し(hタグ)にする
SEOの見出し(hタグ)は、単に目を引く言葉で構成すれば良いというものではありません。最も重要なのは、その見出しを読んだだけで、後に続く本文の内容がある程度イメージできることです。たとえば、「見出し(hタグ)のポイント」といった抽象的な表現よりも、「SEOに効果的な見出し(hタグ)作成の3つのコツ」のように、シンプルかつ具体的で内容を予測しやすい見出しの方が好まれます。検索エンジンも、見出しが本文と論理的に一致しているかを評価の対象としています。読者にとっても、見出しと本文にギャップがあると混乱のもとになり、直帰率や信頼性の低下につながりかねません。したがって、見出しは目立たせるだけでなく、その下の段落が何を説明するのかを的確に示すラベルとしての役割を果たすことが重要です。結果として、検索エンジンにもユーザーにも評価される、構造的で信頼性の高い記事が完成します。
読み進めてもらいやすい表現を意識する
検索結果一覧に表示されるh1やh2は、記事への入り口でもあります。そのため、単に説明的なだけでなく、読者の興味を引く表現が求められます。たとえば、疑問形、数字(例:3つのコツ)、ベネフィット(例:検索上位を狙うための〜)などを入れることで、ユーザーの関心を引く工夫が可能です。基本的に見出しはシンプルにするべきですが、少ない文字数で目を引く表現を入れることができる場合や、他のサイトと差別化する見出しを作成する場合は、このような表現を活用するのも1つの手です。ただし、誇大表現や釣りタイトルにならないよう、見出しと本文の内容が一致していることが前提です。
見出し(hタグ)のフォントを揃える
見出しは構造的に区分されているだけでなく、視覚的にもその階層が伝わるように設計することが大切です。たとえば、h2は太字かつ大きめのフォント、h3はやや小さくシンプルなデザインにすることで、ユーザーは「この項目はh2」「これはその下位のh3」と一目で判断できます。逆に、すべての見出しが同じサイズ・太さ・色で表示されていると、ページ構造が不明瞭になり、情報の流れが掴みにくくなります。また、見出しごとにフォントがバラバラだと、統一感が失われて読みづらくなる原因にもなります。CSSなどであらかじめh2・h3・h4ごとに明確なスタイルを設定しておくことは、可読性の向上やユーザー体験の最適化にも直結するといえるでしょう。
やってはいけない見出し(hタグ)設計の例
ここでは、SEO効果を損なう見出し(hタグ)のNG例と対策を紹介します。
キーワードを詰め込みすぎる
SEOを意識するあまり、見出しに不自然にキーワードを詰め込んでしまうケースは多く見られます。たとえば「h2:SEO 見出し」「h2:SEO タイトル」「h2:見出し キーワード」など、読み手にとって意味が通じにくいキーワードを羅列しただけの見出しは逆効果です。検索エンジンも現在では「自然な文章構造」を重視しており、不自然な見出しは評価されない可能性が高まります。また、ユーザーの視点でも読みづらさや違和感を感じやすく、信頼性を損ねる結果になりかねません。見出しにキーワードを入れる際は、文意を壊さず、自然な日本語になるよう配慮しましょう。
本文と関係ない見出し(hタグ)にしてしまう
見出し(hタグ)に魅力的な言葉を入れようとして、実際の本文の内容と一致していないと、ユーザーの期待を裏切ることになります。これは直帰率や離脱率の増加につながり、SEO評価の低下を招きます。たとえば「5分でできるSEO対策」と書かれていても、実際には5分以上かかる内容や専門的すぎる情報が並んでいる場合、信頼性が下がります。見出しと本文の一致は、ユーザー体験を守る意味でも極めて重要です。記事全体を通して整合性が取れているか、見直しを行う習慣を持つことが大切です。
見出し(hタグ)の階層が乱れている
HTML上でh2の下にいきなりh4を置く、あるいは順序なくh3とh5が混在するなど、論理構造が乱れているケースは意外に多くあります。このような構造は検索エンジンにとってページの内容を正しく理解する妨げとなり、SEO上の不利になります。常に「h2→h3→h4」といった階層順を守り、見出し(hタグ)の数や構造が過不足ないかチェックすることが求められます。
本文が短くなりすぎる場合は新たに見出し(hタグ)を作らない
SEOにおいて見出し(hタグ)は重要な構成要素ですが、内容の薄い段落にまで無理に見出しを付けるのは逆効果になる場合があります。たとえば、本文が1〜2行程度しかないような情報に見出しを付けると、読者はその情報に過度な期待を抱き、実際の内容とのギャップに失望する可能性があります。また、検索エンジンも見出しの後に十分な情報が続かないと、その見出しが適切でないと判断することがあります。見出しはある程度の情報量であれば、目安としては300字程度以上。h3以下であれば100文字以上は欲しいところです)を伴って初めて意味を持つものです。短い情報であれば、既存の見出し内の一部として組み込むか、箇条書きや補足情報として記載する方が自然です。コンテンツの品質を保ち、読者の期待に応えるためにも、「見出しありき」の構成ではなく、情報量とのバランスを考慮した見出し設計が重要になります。
まとめ:SEO見出し(hタグ)を正しく設計して検索上位を目指そう
見出し(hタグ)はSEOの中でも基本かつ重要な要素です。hタグの正しい使い方や、ユーザーの意図に沿った構成、読み進めてもらえる表現を意識することで、検索エンジンとユーザーの双方から評価される記事を作ることができます。見出し(hタグ)は「目に見える構造」であり、SEOで成果を出す基盤です。記事を作成するたびに見直しを欠かさず、質の高いコンテンツへと仕上げていきましょう。