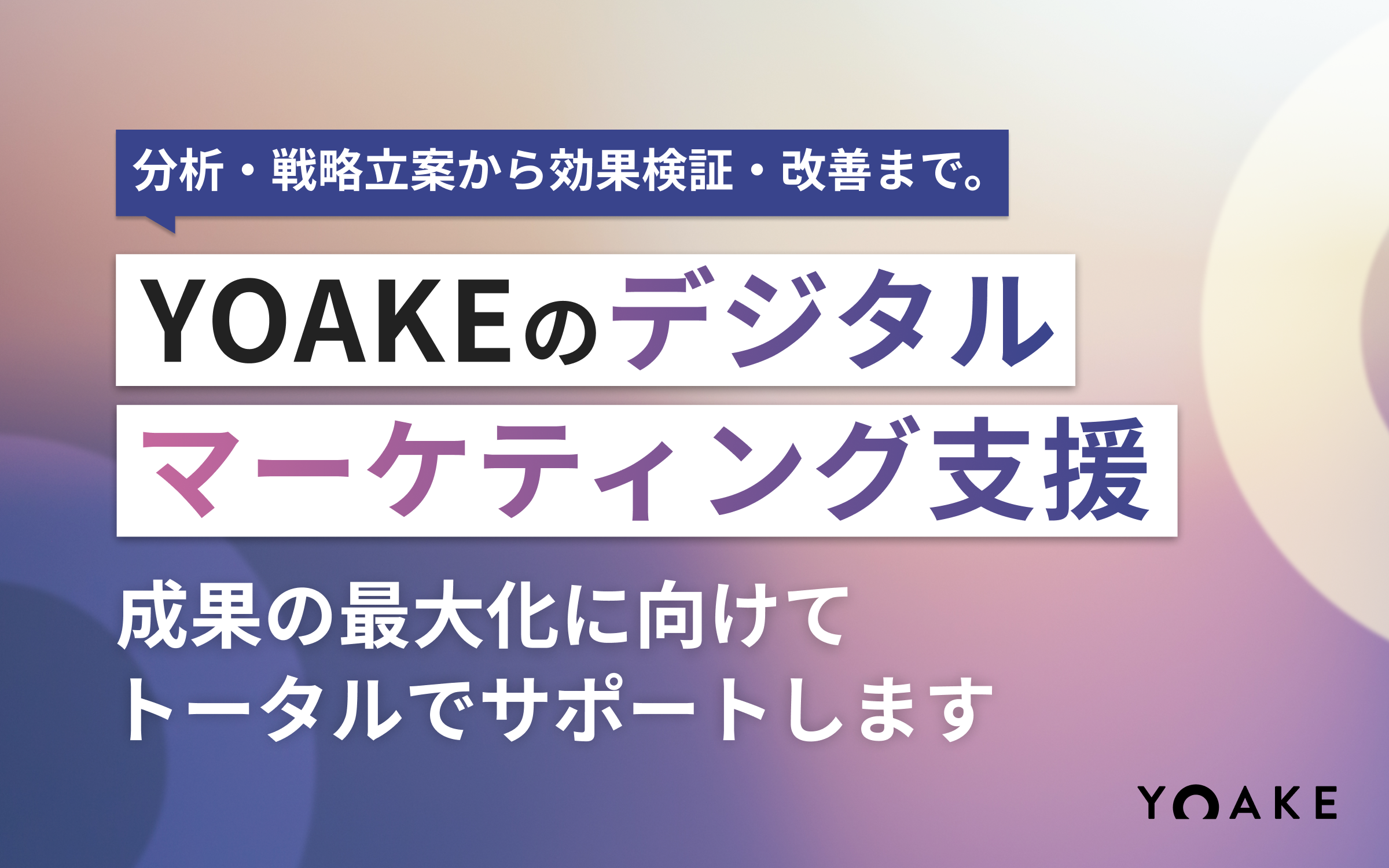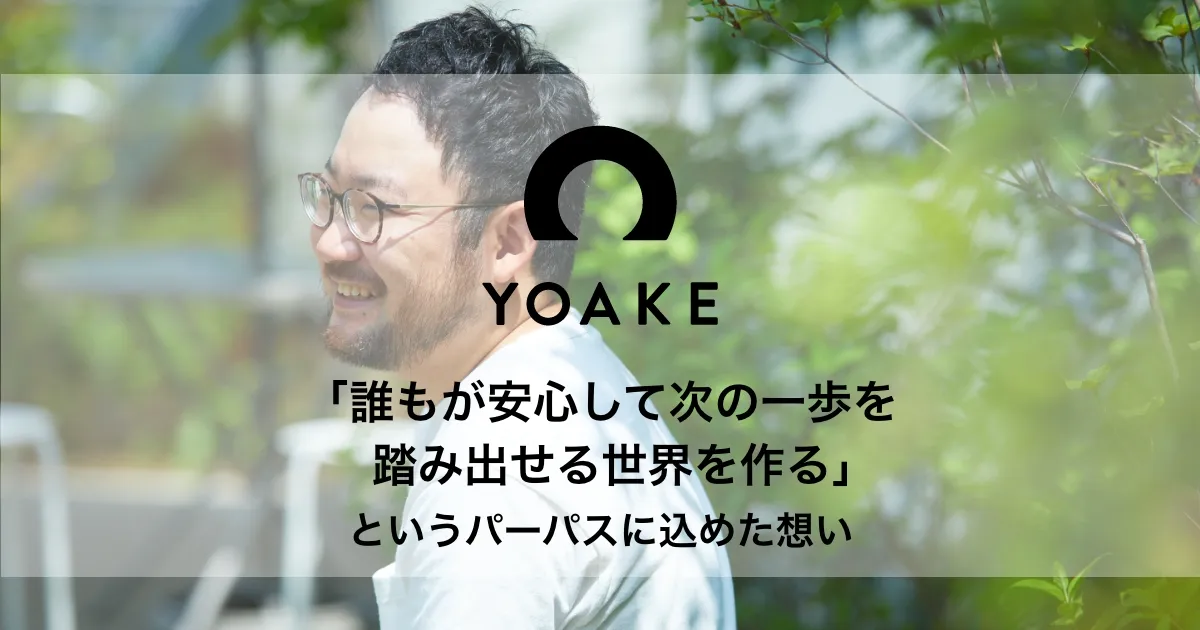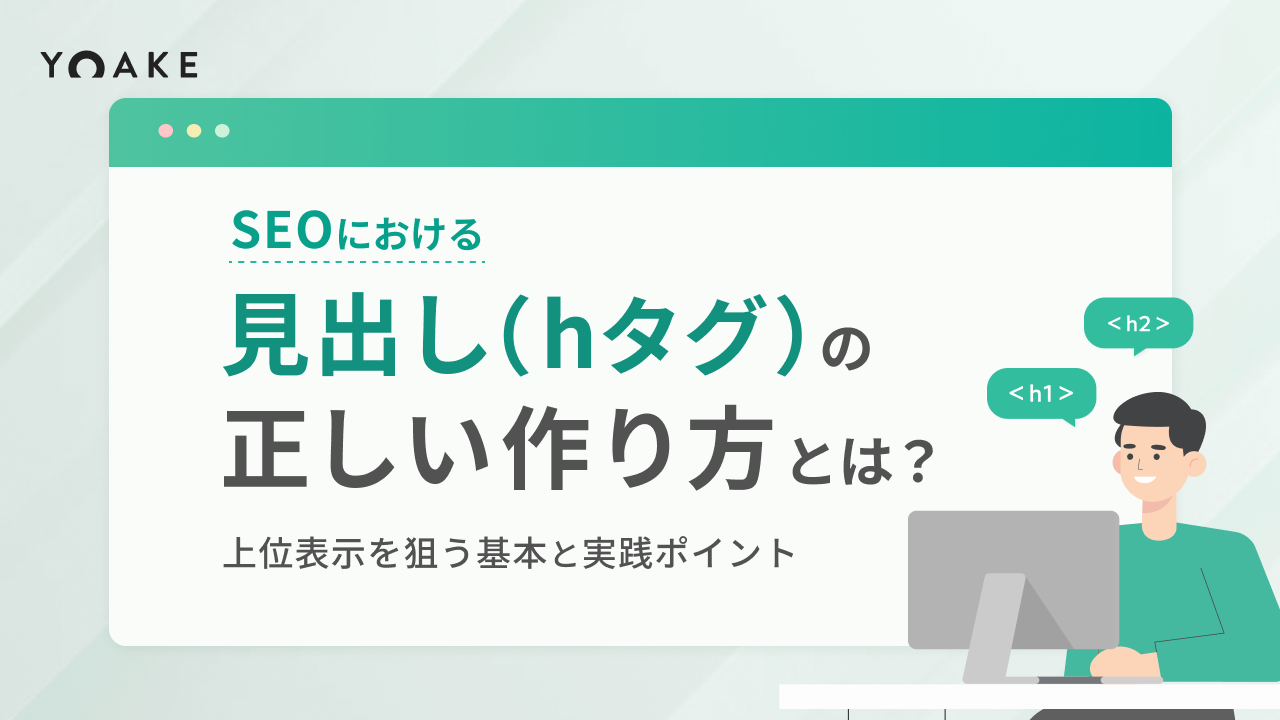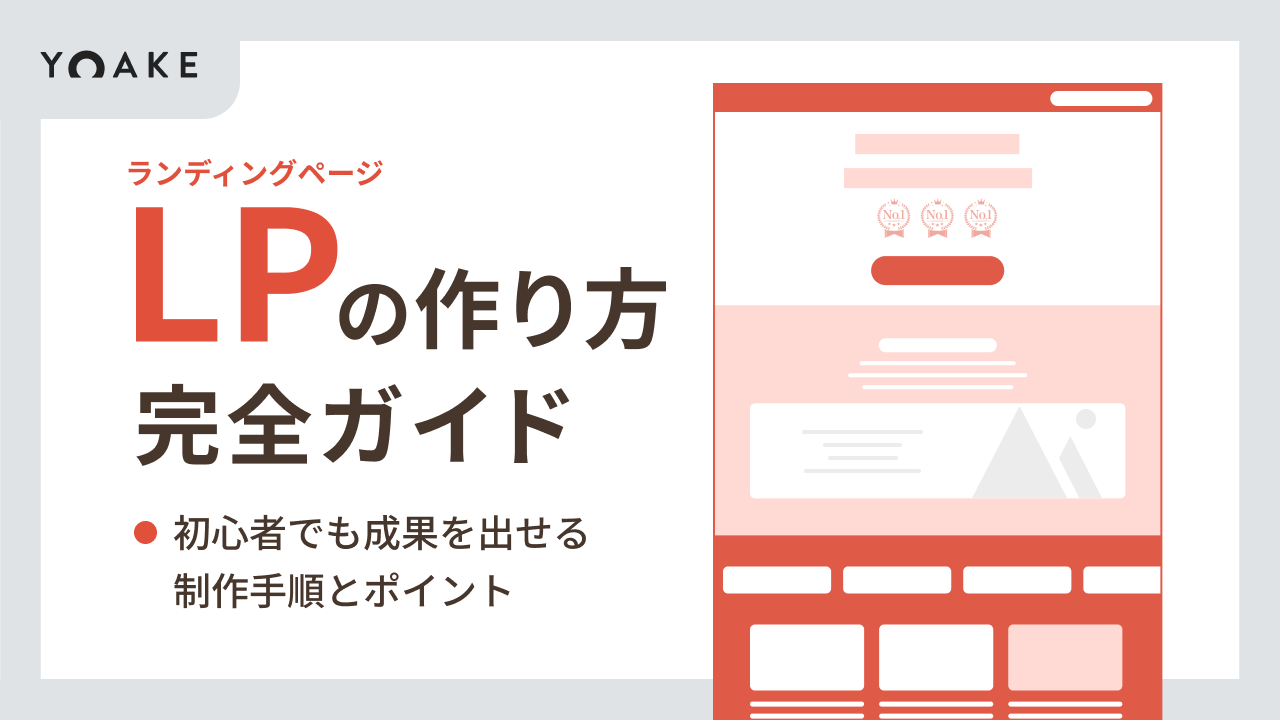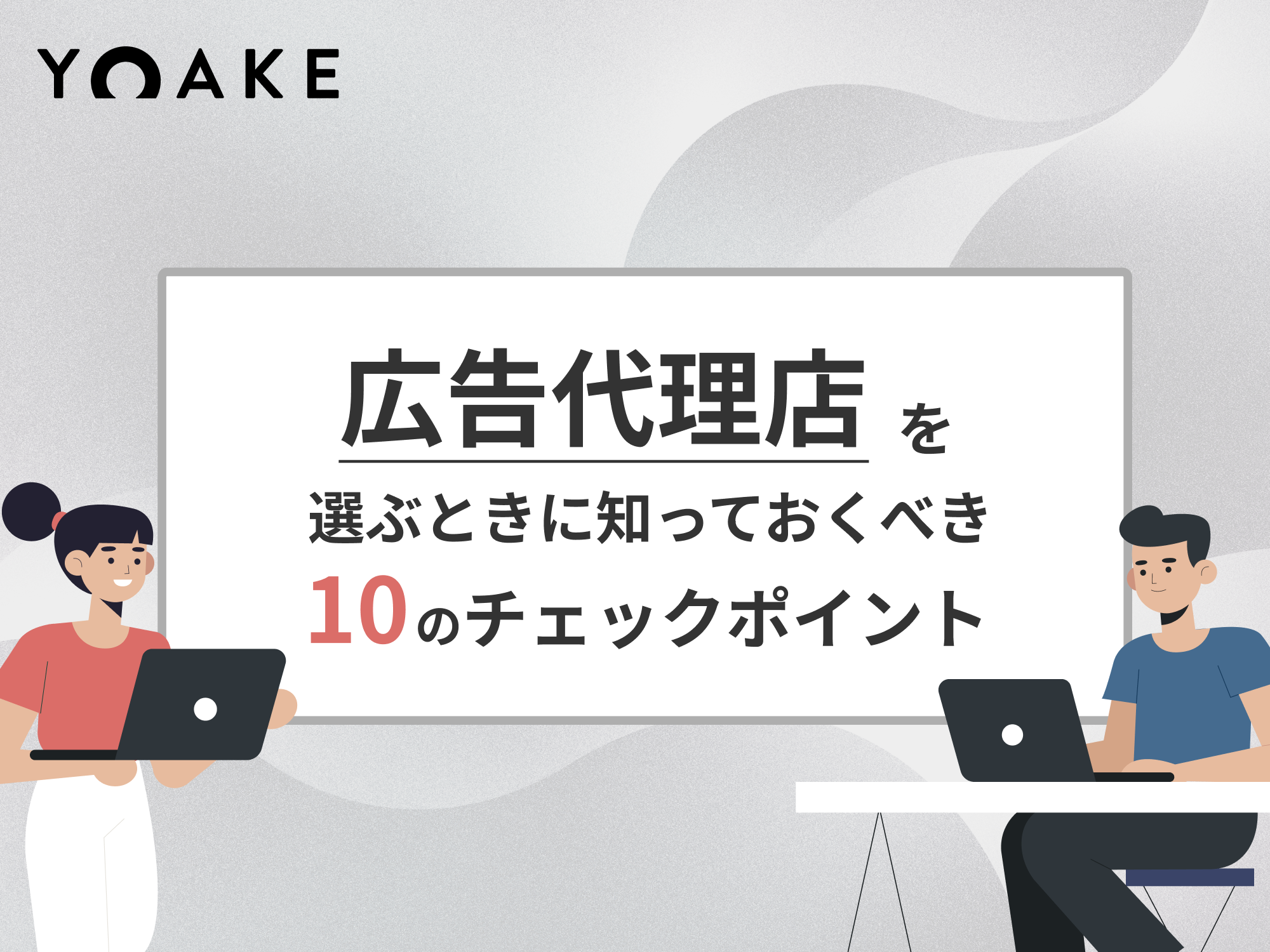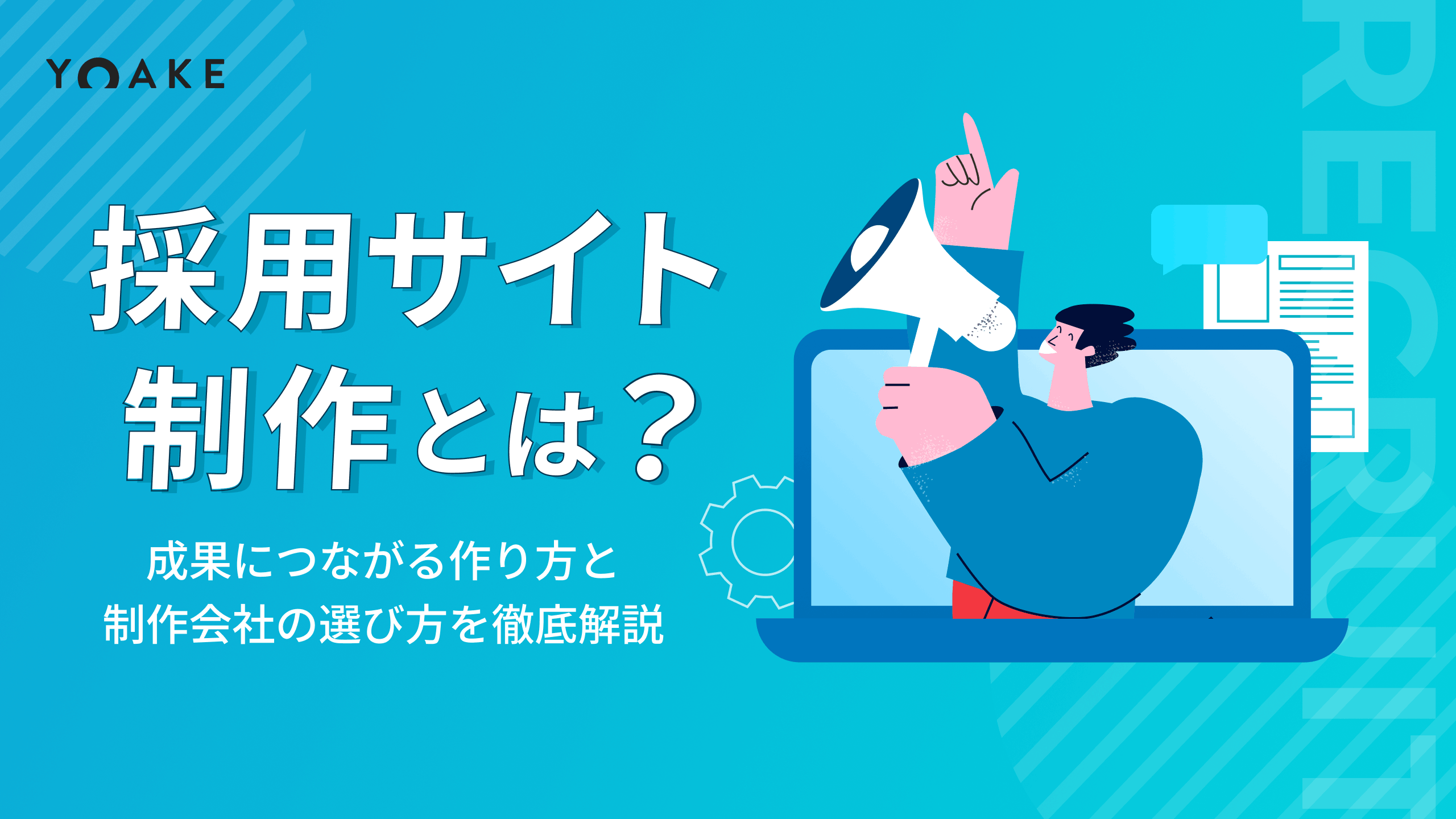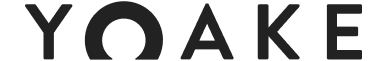BtoBマーケティングとは
BtoBマーケティングは企業などの法人に向けた活動であり、BtoCとは購買の判断基準や進め方が大きく異なります。複数の部門が関わるため検討期間が長く、導入リスクや費用対効果を慎重に見極める傾向があります。また、商談規模が大きいことから、営業とマーケティングが協力して価値提案を行わなければ成果につながりません。さらに、顧客企業の課題構造や業界の特性を深く理解し、相手の業務改善につながる提案が求められるでしょう。こうした理由から、BtoBでは計画的な戦略設計と継続的な改善が不可欠です。
BtoBマーケティングの全体プロセス
ここでは、BtoBマーケティングがどのように商談・受注につながるのか、その全体像を整理します。
リード獲得(リードジェネレーション)
リード獲得は、見込み顧客との最初の接点をつくる重要な工程です。担当者は自ら情報収集を進めるため、検索流入や広告、ホワイトペーパーなど、複数の経路から興味を示します。効果を高めるには、課題解決につながる情報や事例を提示し、必要な資料を適切なタイミングで入手できる状態を整えることが欠かせません。また、LPの改善やCTA設計を見直すことで、問い合わせ率が向上しやすくなります。さらに、潜在層向けに課題に気づいてもらうコンテンツを提供すれば、将来的な商談の母数も増えるでしょう。リード獲得の質は後工程に直結するため、戦略的な仕組みづくりが必要です。
リード育成(リードナーチャリング)
リード育成は、獲得した見込み顧客に対して「関心の深化」と「検討度の向上」を促す工程です。BtoBでは検討期間が長いため、適切な情報提供を継続しなければ候補から外れてしまう可能性があります。メールマーケティングやウェビナー、成功事例の共有など、顧客が次のステップに進むために役立つ情報を段階的に届けることが重要です。また、MAツールを活用すれば、行動データをもとに興味関心を判断でき、より精度の高いコミュニケーションが実現します。営業との連携によって必要な情報を共有すれば、商談化までの流れがスムーズに進むでしょう。ナーチャリングの質は受注率に直結するため、計画的な運用が求められます。
リード選別(リードクオリフィケーション)
商談化・受注の段階では、育成・選別されたリードを営業が引き継ぎ、具体的な提案へ進めます。BtoBでは導入後の運用や社内調整まで考慮されるため、提案の根拠や実績を分かりやすく示す姿勢が求められます。顧客が抱える課題を整理し、導入効果を定量的に説明できれば、意思決定を後押ししやすくなるでしょう。また、営業とマーケが行動データや関心領域を共有することで、顧客にとって関連性の高い提案が可能になります。検討が長期化する場合は、事例紹介や情報提供を継続し、コミュニケーションを途切れさせないことが成約率の向上につながります。
継続利用・アップセル・クロスセル
BtoBでは、受注後の関係構築が収益に大きく影響するため、継続利用を促しながらアップセル・クロスセルにつなげる取り組みが欠かせません。導入効果を最大化するためのサポートを行い、顧客の成功体験を増やすことで、追加提案が受け入れられやすくなります。また、利用状況や問い合わせ内容を分析すれば、潜在的なニーズを把握でき、適切なタイミングで別サービスを案内できるでしょう。さらに、定期的なコミュニケーションを維持することで信頼関係が深まり、解約リスクの低減にもつながります。既存顧客は新規よりも成約率が高いため、このフェーズに注力することが企業の成長を後押しします。
BtoBマーケティングの戦略設計ステップ
ここでは、成果につながるBtoBマーケティングの戦略をどのように設計していくか、基本的な流れを整理します。
市場環境・競合・顧客課題の調査・分析
戦略設計の最初の工程は、市場や競合の状況、そして顧客が抱えている課題を正確に把握することです。BtoB領域では、表面的なニーズだけを捉えても効果的な戦略につながらないため、業界構造や導入の背景まで深く理解する姿勢が重要になります。競合のサービス内容や価格設定、提供価値を整理すれば、自社の立ち位置も明確になるでしょう。また、既存顧客へのインタビューや社内データの分析を通じて、課題の根本原因を見極めることができます。こうした調査によって得られた情報は、ターゲット設定や訴求軸の精度を高めるうえで欠かせません。
マーケティング戦略の策定(ターゲット・価値提供・手段設計)
戦略策定では、まず「どの企業・担当者に価値を届けるのか」を具体的に定め、顧客が抱える課題や期待する成果を正確に把握します。次に、自社が提供できる強みを整理し、他社と比較した際の優位性を明確にすることが重要です。そのうえで、SEOや広告、資料DL、ウェビナーなど、価値を最も効果的に伝えられる手段を組み合わせ、戦略全体を設計します。ターゲット・価値・手段が一貫しているほど、施策の精度が高まり成果につながりやすくなります。
施策の実行と改善サイクル
施策の実行段階では、戦略で定めたターゲットや訴求軸に沿って、SEO、広告、メール、ウェビナーなどの具体的なアクションを展開します。ただ実行するだけでは成果が安定しないため、データをもとに効果測定を行い、改善点を見極める姿勢が欠かせません。問い合わせ率や資料DL数、商談化の流れを観察することで、強化すべきポイントが見えてきます。施策を実行し、結果を分析し、改善を繰り返すサイクルを継続することで、成果が積み上がり、再現性の高いマーケティング運用が実現します。
BtoBマーケティングの主要手法一覧
ここでは、BtoB企業が成果を高めるために活用する代表的な施策を、個別の手法ごとに解説します。全部で20個以上の施策を簡単に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
SEO
SEO(検索エンジン最適化)は、見込み顧客が課題を検索した際に自社サイトを発見してもらうための施策です。BtoBでは担当者が自主的に情報収集を行うため、検索上位を確保できれば早期の候補入りにつながります。専門性の高い記事や事例を整備することで信頼獲得にも寄与し、継続的な流入が期待できる点も強みです。長期的な資産になる取り組みといえるでしょう。
リスティング広告
リスティング広告は、検索キーワードに連動して広告を表示し、課題を持つ顧客に直接アプローチできる手法です。BtoBでは「サービス名+比較」「導入検討」など、意図が明確な検索が多いため、効率的なリード獲得が期待できます。短期間で成果につながりやすく、SEOやLP改善と組み合わせることで相乗効果を生む施策です。
ディスプレイ広告
ディスプレイ広告は、バナーなどを通じて潜在層へ広く認知を届ける施策です。検討初期に接点をつくりやすいため、サービスを知らない層へ情報を届けたい企業に向いています。また、リターゲティング用として利用すれば、過去にサイトを訪れたユーザーに再度接触でき、検討の後押しにつながります。幅広い目的で活用できます。
SNS広告
SNS広告(Facebook/LinkedInなど)は、ターゲットの業種・職種・興味に合わせて精度高く配信でき、BtoBとの相性も良い施策です。特にLinkedInは職種データが豊富で、BtoB商材のリード獲得に効果を発揮します。ウェビナーの集客や資料DLとも組み合わせやすく、短期間で成果が出やすい点もメリットです。認知から獲得まで幅広く利用できます。
リターゲティング広告
リターゲティング広告は、一度サイトを訪れたユーザーに再び広告を届ける施策です。BtoBでは比較検討が長いため、何度も情報収集を行う担当者が多く、再接触による効果が出やすい領域です。資料DLやLP閲覧者に絞って配信すれば、検討度の高い層へ効率的にアプローチできます。成果につながりやすい代表的な広告手法です。
LP制作・改善
LP(ランディングページ)は、問い合わせや資料DLなど、特定のアクションに誘導するためのページです。BtoBでは、導入効果・機能・事例・料金など、担当者が判断するうえで必要な情報を明確に示すことが重要になります。CTAの配置や構成を改善すれば、コンバージョン率が大きく向上します。広告やSEOと連動することで成果がさらに高まり、獲得効率も改善されます。
Web接客
Web接客(チャットボットなど)は、サイト訪問者の状況に合わせて自動で案内を行う仕組みで、チャットボットやポップアップなどが活用されます。必要な情報にすぐアクセスできるため、離脱の防止や資料DLの促進に役立ちます。BtoBでは、製品選びに迷う担当者をサポートし、問い合わせにつなげる効果も期待できます。改善しながら精度を高められる点も魅力です。
ホワイトペーパー施策
ホワイトペーパー(資料DL)は、顧客が課題を深く理解するための詳細資料を提供し、見込み顧客情報を取得するために有効です。BtoBでは具体的な数値や導入事例を求められるケースが多く、質の高い資料は意思決定プロセスの初期段階で強い影響を与えます。DL後のメール施策とも組み合わせやすく、育成の起点として活用できます。
ウェビナー
ウェビナー(オンラインセミナー)は、オンラインで専門情報を提供し、見込み顧客との接点を増やす施策です。場所を選ばず参加できるため、興味を持つ担当者を集めやすく、課題整理や製品理解を促進できます。質疑応答によって顧客のニーズを把握できる点も利点で、商談につながるケースも多く見られます。育成と獲得の両方に効果的です。
メールマーケティング
メールマーケティング(メルマガ)は、見込み顧客に継続的に情報を届け、検討度を高めるための手法です。ウェビナー案内や事例紹介など、段階に応じた内容を届けることで、自然な形で次の行動を促せます。BtoBでは検討期間が長いため、途切れないコミュニケーションが信頼形成に役立ちます。MAツールとの連携で精度も上がります。
MA活用
MA(マーケティングオートメーション)は、見込み顧客の行動データをもとにスコアリングやメール配信を自動化し、効率的に育成を進めるためのツールです。BtoBでは検討期間が長いため、興味の変化を可視化できる点が大きな強みになります。資料DLやサイト閲覧履歴を把握することで、営業へ引き渡すタイミングも判断しやすくなります。運用次第で商談化率が向上します。
SNS運用
SNS運用(情報発信・企業ブランディング)は、専門情報や実績を継続的に発信し、企業の信頼やブランドを築くための取り組みです。BtoBでは即効性は高くありませんが、業界知見を発信し続けることで潜在層との関係が深まり、将来のリード獲得に寄与します。採用やパートナー開拓にも効果があり、長期的な企業価値向上につながる施策として位置づけられます。
外部メディアへの出稿
外部メディアへの記事広告やタイアップは、専門性の高いメディアの信用力を借りて情報を届けられる点が強みです。BtoB商材は自社だけでは説明が難しいことも多く、第三者の視点で価値を整理してもらうことで理解が深まります。認知獲得からリード獲得まで幅広く活用でき、SEOにも寄与するケースがあります。
プレスリリース配信
プレスリリースは、新サービスや導入事例などをメディアに届け、広く情報を伝えるための施策です。BtoBでは信頼性が重視されるため、公式情報として扱われるリリースはブランド価値の向上に貢献します。メディア掲載をきっかけに問い合わせが増えるケースもあり、認知拡大や営業支援としても活用しやすい手法です。
展示会出展
展示会出展は、見込み顧客と直接対話しながら製品やサービスを訴求できる貴重な機会です。BtoBでは担当者が実物を見たり話を聞いたりして理解を深めるため、オンラインでは得られない納得感が生まれます。名刺交換によるリード獲得にも向いており、商談の糸口がつかめる施策です。出展後のフォローによって成果が大きく変わります。
インサイドセールス
インサイドセールスは、電話を通じて見込み顧客の状況を確認し、商談化の可能性を探る手法です。メールでは反応が得られにくい担当者にもアプローチでき、課題を直接ヒアリングできる点が強みです。BtoBでは検討状況が企業ごとに異なるため、会話を通じた情報収集が役立ちます。営業と連携することで成果が高まります。
フィールドセールス
フィールドセールス(訪問営業)は、訪問を通じて顧客課題を詳細に把握し、最適な提案を行うための手法です。実際の業務環境を確認できるため、より実践的な価値訴求が可能になります。BtoBでは複雑な導入を伴う商材も多く、対面での説明によって不安解消が進みます。ナーチャリング後の最終段階で効果を発揮する重要な役割です。
DM施策
DM(ダイレクトメール)施策は、郵送物を通じて特定の担当者に直接アプローチできる手法です。メールよりも開封率が高い場合があり、資料やサンプルを同封することで興味を持ってもらいやすくなります。BtoBでは「まだ課題を自覚していない層」への接触にも有効で、展示会案内や事例集の送付などにも活用できます。営業活動の補完として機能します。
紹介営業
紹介営業(リファラル)は、既存顧客やパートナー企業から新たな見込み顧客を紹介してもらう手法です。第三者からの推薦で始まるため信頼度が高く、商談化や受注までのスピードが速い傾向があります。BtoBでは実績や評判が重要視されるため、相性の良い企業からの紹介は大きな価値を持ちます。満足度の高い顧客を増やすことが、紹介の連鎖を生み出します。
マス広告
マス広告は、テレビやラジオを活用して大規模な認知を獲得する施策です。BtoB企業にとっては一般的ではありませんが、ブランドを大きく成長させたい場合や、幅広い業種へ一気に認知を広げたい場面で効果を発揮します。信頼感や企業の存在感を高めやすく、採用やパートナー開拓にも寄与します。長期視点で活用したい施策です。
交通広告
交通広告は、駅や電車内で広範囲に情報を届けられる手法で、特定地域や職種に向けた訴求がしやすい点が特徴です。BtoBでは、都心のビジネスパーソンに絞ったアプローチが可能で、ブランド認知を一気に高められます。オンライン施策と組み合わせれば、検索数やサイト流入の増加につながり、検討のきっかけを生み出します。
アカウントベースドマーケティング
アカウントベースドマーケティング(ABM)は、狙いたい特定企業に焦点を絞り、営業とマーケが協力して最適なアプローチを行う手法です。幅広く集客する従来型とは異なり、重点アカウントに深く入り込むことで高い受注率が期待できます。企業ごとに課題を分析し、最適なコンテンツや提案を届けることで関係性を強化できます。大口顧客の獲得にも効果的です。
カスタマーサクセス
カスタマーサクセス(CS)は、顧客の成功体験を支援し、継続利用や追加契約につなげる取り組みです。導入後の成果を定期的に確認し、改善提案を行うことで、顧客の満足度を高められます。BtoBでは解約防止に直結するため、重要度の高い施策です。データを活用して利用状況を把握すれば、アップセルやクロスセルの機会も増やせます。
BtoBマーケティングの市場と今後【2025年の動向予想】
ここでは、BtoBマーケティングが今後どのように変化していくのか、2025年を見据えた主要トレンドを解説します。
トレンド1.生成AI
生成AIは、BtoBマーケティングのプロセスを大きく変革しており、業務効率だけでなく、企画や分析の質そのものを引き上げています。ブログ記事やホワイトペーパーの構成案、メール文、バナーコピーなどを短時間で作成できるため、担当者はより戦略的な業務に集中しやすくなります。また、顧客データをAIが自動で読み取り、関心の変化や検討段階を推測する活用例も増えています。精度の高い分析が可能になることで、ナーチャリング施策の改善や営業連携の質も向上します。2025年以降は、生成AIがマーケティングの基盤として組み込まれる流れがさらに強まるでしょう。
トレンド2.LLMO
LLMO(Large Language Model Optimization)は、生成AIを前提とした検索環境で、ユーザーに最適な情報を提示するための新しい最適化手法です。従来のSEOが検索エンジン上位獲得を目指すのに対し、LLMOはAIが回答を生成する際に“参照に値する情報”を提供することを目的とします。信頼性の高いデータ、明確な根拠、体系的な構成が重要視され、一次情報や事例の充実度が評価に直結します。また、AIに引用されやすい形式でコンテンツを設計する必要があり、文章の構造化や専門性の担保が欠かせません。2025年以降、BtoBマーケの情報発信は「AIに強いコンテンツ」を作る視点への転換が進むでしょう。
トレンド3. 一次情報の重要性
一次情報は、AIや検索エンジンの評価基準として重視されており、BtoBマーケティングでも必須要素になりつつあります。自社調査データ、ユーザーインタビュー、導入事例、運用ノウハウなど、独自性のある情報は信頼性を高め、競合との差別化にもつながります。特に2025年以降は、AI検索が一般化することで、ネット上でよく見かける一般論では価値が生まれにくくなります。深い業界知識や現場のリアルに基づくコンテンツは、検討段階の顧客に大きな影響を与えるため、リード獲得にも直結します。事業活動と連動した情報発信が、今後の競争力の源泉になるでしょう。
トレンド4.動画の活用拡大
動画は、サービス理解を促進しやすく、知識レベルの異なる複数の担当者に同時に情報共有できる点が強みです。BtoBでは製品デモ、顧客インタビュー、ウェビナーのアーカイブなど、視覚的に伝えることで理解が深まりやすい場面が多くあります。また、短尺動画をSNSやLPで展開すれば、担当者の初期興味を引き出す効果も期待できます。AIを活用すれば字幕生成や編集が容易になり、動画制作のハードルも大幅に下がっています。今後は、文章や資料だけでは伝わりにくい複雑な価値を動画で補完するスタイルが主流になるでしょう。
トレンド5.コンテンツマーケティング
コンテンツマーケティングは、以前からBtoB領域で最も重要度が高い施策の一つです。検討の初期段階では担当者が自ら情報収集を行うため、課題理解を助ける高品質な記事や事例、調査レポートが意思決定に強い影響を与えます。2025年にかけては、単なる情報提供ではなく、一次データや独自視点を反映した「深いコンテンツ」が求められるようになります。また、生成AIの普及によって一般的な文章の価値が下がる一方、自社の専門性を表すコンテンツは差別化の核となります。動画、図解、ケーススタディなど多様な形式を組み合わせることで、信頼性と理解度を高められる点も大きな利点です。
まとめ
BtoBマーケティングは、複数の意思決定者と長い検討期間を前提に、顧客理解・営業連携・データ活用を軸に進めることが重要です。高品質なコンテンツやMAによる育成を組み合わせることで商談化率が高まり、継続利用やアップセルにもつながります。生成AIやABMなど新しい手法も取り入れ、仕組みとして最適化することが成果向上の鍵になります。
YOAKEは、BtoBマーケティングの支援はもちろん、SEO、広告運用、分析・改善体制の設計、CRMやサイト改善など、デジタルマーケティング全般に強みを持つパートナーとして、企業ごとの課題や目的に合わせた最適なスタイルをご提案しています。部分的な内製化から全体戦略の構築まで、幅広くご支援可能です。「これからBtoBマーケティングを強化したい」「自社の体制を見直したい」と感じたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。